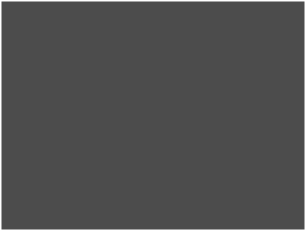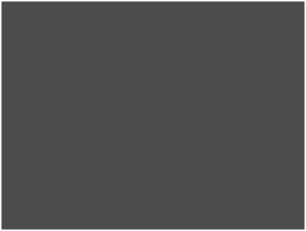Période de Madame de Pompadour / Rokoko Period(1756-1764)

Sevres(1756-Present) France
Période de Marie Antoinette /Période néoclassique(1770-1789)

Période de Transiti(1765-1769)
<移転>
1756年、ヴァンセンヌ窯は古い城が手狭になり、セーヴルに建設した新しい工場に移転した。1759年にはフランス国王が単独オーナーになり、名実共に国立磁器製作所となった。
技術総監督に王室金細工師のジャン・クルード・デュプレシー(Jean-Claude Duplessis)、装飾監督のジャン・ジャック.バシェリー(Jean-Jacques Bachelier)、彫像監督のエティエンヌ・モーリス・ファルコネ(Etienne-Maurice Falconet)、絵付け監督のフランソワ・ブーシェ(François Boucher)ら、錚々たるメンバーが名前を連ねた。
<グラウンド・カラー>
1745年代のヴァンセンヌ窯では、まだセーヴル窯独自の作品を生み出すまでには至っていなかった。 しかし1750年代に入り、ヴァンセンヌ窯では、様々な顔料が開発され、清の粉彩を模して、一面に染めてしまうグラウンド・カラー( la couleur de fond )が開発された。
先ず初めに開発されたのがブルー・ラピス(Bleu Lapis)でヴェネツィアのガラスを原料にしたコバルトを含む顔料で、釉薬を掛ける前のビスキュイ(biscuit)の段階で、染め上げたい部分に振りかける。しかし往々にしてムラが出来易く、また境界部分がどうしても不明瞭になる。その為に境界部分を金彩で縁取る事を常としていた。またこの金彩に細かい装飾を施す事もセーヴルの特徴であった(但し1763年にブルー・ヌーヴォー(Bleu Nouveau/ Beau Bleu No.2)が開発され、より鮮やかなグラウンド・カラーが頻用される様になった)。
次ぎのグラウンド・カラーは、化学者エローが開発した鮮やかなトルコ・ブルーでブルー・セレスト(Bleu Céleste)(天の青)または、ルイ15世サーヴィスに使用され、また王が好んだ色でもあったので、ブルー・ドゥ・ロワ(Bleu du Roi)(王の青)とも呼ばれた(但しエローは1755年に更に改良し、より明るい発色の顔料となっている)。
引き続いて、1756年のセーヴル初年にはヴェール(Vert)(緑)、1757年にはロース(Rose)(ピンク)、1758年からは、2色を組み合わせて、トゥー・カラー・グラウンド(ブルー・ラピスとヴェールなど)が、更には3色組み合わせたグラウンド・カラーの作品も制作された。
<ギルディング>
またセーヴル窯は、1745年のヴァンセンヌ時代に獲得した特権により、磁器への金彩装飾の使用を唯一の王立窯として独占していた。しかし当初、どの程度の金彩技術があったかは明確では無い。1748年、エローはヴェネディクト派僧侶・イポリテュ・ルフォル(Hypolite Lefaure)(フレール・イポリテュ(Frère Hypolite))から3000リーヴル以上の現金で、金彩に使う金箔の納入契約を結んだ記録が残っている。
また創業者であるフリュヴィーの財産目録には、ヴァンセンヌ城内の一室を、イポリテュに提供した記録が残っている。
こうして得られた金箔は、エローの記録ではニンニクのペーストを混ぜて、ちょうど良い粘稠度に調節して、筆で金彩装飾を施したようであるが、後の技術監督のジョルジ・ヴグテュ(Georges Vogt)は、1893年に混ぜていたのは(ウースター窯と同じ)蜂蜜であると断言している。何れにしてもさらさらの金に粘度をもたらし、焼成後に焼失するものを混入させたものと考えられる。
1766年にエローが亡くなると、1770年代にかけて多くの技術革新が行われた。
例えば金箔をそのまま使ったエカテリーナ2世の為のサーヴィスが良い例である。また 1760年代からの新古典主義への移行にともない、金彩技術も多彩になり、部分的に酸化させて輝きを失わせたり、それまでのマイセン風のレッド・ゴールドから、イエロー・ゴールドと、グリーン・ゴールドを組み合わせたローアン・サーヴィス(Rohan Service)のモノグラムなど、金の色合い、趣向も移り変わって行った。
この様な手のかかる金彩装飾の作業は、原則として女性の職人によって行なわれ、彼女達は芸術監督より、充分な教育を受け、手厚い待遇を受けていた(職人の待遇は、当時非常に低いモノであった)。
また個別の磁器の価格は、このような金彩の品質に大きく影響された。
<ホワイト・ディプロマシー>
このようにフランスの粋を集めて制作されたセーヴル窯の食器セットは、フランスの外交政策の一助として利用された。
18世紀のフランスは、金や銀が不足し、ルイ14世の死後、多大な国の負債が顕在化し、世紀の始めはジョン・ローに改革を委ねたが失敗。その後の度重なる戦争で、ますます経済的に危機的状態にあった。
サロンを開いてフランスのロココ芸術を推進していたポンパデュール侯爵夫人は、オーストリア継承戦争での敵国であったオーストリアのマリア・テレジア(Maria Theresia)と手を組み、今やザクセンを脅かして急成長するプロイセンのフリードリヒ大王(Friedrich der Große)との間で七年戦争を闘い、結局敗戦して責任を取って失脚、失意の中で1763年に亡くなった。
時代はポンペイ遺跡の発掘を契機に古代ローマの文化が見直され、つかの間のロココから再び古典主義に向っていた(ルネサンスがギリシアだったのに対して今回はローマ文化の再興であった)。
ポンパデュール侯爵夫人の肝入りで国費を投入して操業していたセーヴル窯は、まさに国威の象徴であり、ヨーロッパ最高水準で、最先端の芸術作品を生み出していた。
七年戦争にあたっては、同盟関係が逆転し、近隣国との関係性の証しとして、ポンパデュール侯爵夫人は各国にセーヴル磁器を贈っていた。まさに「白い外交」(White Diplomacy)と呼ばれる所以である。
1756年に戦争が始まると、1758年に中立国のデンマークのフレデリック5世(Frederik V)に食器セットを贈り、1759年には同盟の証しにオーストリアのマリア・テレジアに、1760年には中立国維持を求めて、ファルツ選帝侯のカール・テオドア(Karl Theodor)にも鳥の絵の装飾の食器セットを贈っている。
果たしてこの習慣はポンパデュール侯爵夫人の死後も継承され、1768年にはデンマークのクリスティアン7世(Christian Ⅶ)に、1770年にはスウェーデンのグスタフ3世(Gustav Ⅲ)に、そして1770年、オーストリアからマリー・アントワネット(Marie Antoinette)がドンファン亡き後の王位継承者である皇太子ルイ(Louis)と結婚すると、1773年には、マリー・アントワネットの姉で、ナポリ・シチリア王のフェルディナンド4世(Ferdinando Ⅳ)(ナポリ窯を創設)に嫁いだ、マリア・カロリーナ・ルイーザ・デ・ナポリ(Maria Carolina Luisa de Napoli)の出産祝いに、食器セットが贈られているが、このセルヴィスにはカロリーナ・ルイーザのイニシャル、C、Lが装飾として入れられている。ブルボン家の結束を固める政策の中(パクテュ・デュ・ファミーユ/Pacte de Familleという)で、更に1774年、スペイン王カルロス3世の息子でアステュリア皇太子(Principe de Asturias)(後のスペイン王カルロス4世)と、ルイ15世の孫娘のマリア・ルイーザ・デ・パルマ(Maria Luisa de Parma)との結婚を記念して、アステュリー・セルヴィスがルイ15世によって発注された。
同盟関係は、当時フランス、スペイン、パルマ、ナポリとシチリア、ザクセンからオーストリアまで広がり、各国はローマカトリックへの信仰でも共通していた。
<フィギュリーヌ>
食器や花瓶などの装飾品とともに、セーヴル窯の磁器の彫像も、外交的に利用された。
磁器の彫像は、ヴァンセンヌ窯の1740年代より制作されていた。
これらの磁器の彫像は主に晩餐会でのデザート用のテーブルに置かれるセンターピースとして、それまでの富の象徴として造られていた砂糖でできた彫像の替わりに制作される様になったものである。
そもそもヨーロッパにおける食習慣は、古代ローマ時代の影響を色濃く残している。
コース料理はローマ時代から存在する。
食事は長テーブルの上に載せてテーブルごと運ばれて提供され、エトルリア人の墓石の彫像のごとく、左半身を下にして横向きなって食事を頂く。
コースは大きく ❶グスターティオ(Gustatio=味覚、前菜)
❷メンサ・プリマ(Mensa Prima=第1のテーブル、主菜)
❸メンサ・セコンダ(Mensa Seconda=第2のテーブル、デザート)
に分かれる。この時代はテーブルごと各コースが運ばれてくる訳だが、イタリアルネサンス期の宮廷では、今のイタリアのように、❶がアンティパスト、❷がプリモ・ピアットとセコンダ・ピアットそして❸がドルチェに当たり、❷から❸へ行く所で部屋を変えて、そこで色々な余興が行われた。
この習慣はイタリアからアルプスを超えてフランスに渡り、ヨーロッパ中に広まった。
また当時は、大きなテュリーンなどに作った料理を入れ、テーブルまで運び、それを一人ずつ取り分けるなどして、テーブルで給仕された。 今の様に一人ずつお皿に盛って提供するやり方は、ロシア式と言われている。
宮廷における晩餐会は一つの儀式であり、自分が何処に座るかが重要で、給仕係りも名誉な仕事であった。それは一つの、お互いの階級や身分を確認する場でもあった。
そしてその食事と一緒に催される余興は、主人が来賓をもてなす、非常に重要な催しであった。
そのテーブルの上に飾る為の彫像として制作された磁器像は、ヴァンセンヌ窯では1748年までは上絵付けをして装飾されていた。1751年から1752年までは白磁でも釉薬が掛けられていたが、1750年頃より装飾監督のバシェリーの指導のもと、無釉のビスクィ(Biscuit/語源は2度焼成や、ビスケットに風合いが似るなど諸説有り)の制作を始め、1752年以降はほぼ全てビスクィとなった。
実は釉薬を掛ける作品よりも、釉薬を掛けない作品の方が素地の品質がハッキリと出てしまう。つまり歩留まりの悪い軟質磁器の焼成で、しかもビスクィを制作すると言う事は、技術の進歩があるにせよ、かなりのコストを覚悟する必要がある。
こうして1752年以降、セーヴル窯を代表するビスクィの彫像が、採算を度外視して制作されることとなった。
これらの彫像は、ロココ芸術を主導したポンパデュール侯爵夫人の後援のもと、ブーシェの銅版画などを元絵として、それを三次元の彫像へと作り替えていった。
それらの困難な作業を行った彫刻師の代表が、ファルコネであった。
1750年代に在籍した彫刻師は、ファルコネの他に、ピエール・ブロンドゥ(Pierre Blondeau)、ルイ・フェリックス・ドゥ・ラ・ルー(Louis-Felix de La Rue)、ジャン・バプティスト・フェルネ(Jean-Baptiste Fernex)、クロード・ルイ・スザンヌ(Claude-Louis Suzanne)らが名を連ねた。
幾つかのビスクィの原型は、その彫刻師が同定されているが、そのビスクィ自体を誰が制作したかの同定は難しい。
18世紀のビスクィにはアルファベットの刻印が入るが、下のリストの様に、それは制作者では無く、彫刻部門のその時の監督者のイニシャルである。
彫刻部門の監督
1757年ー1766年/エティエンヌ・モリス・ファルコネ(Etienne-Maurice Falconet)/F
1766年ー1773年/ジャン・ジャック・バシュリエ (Jean-Jacques Bachelier)/B
1773年ー1780年/ルイ・ブワゾ(Louis Boizot)/Bo
1780年ー世紀末/ジョセ・フランソワ・ジョセフ・ル・リーシェ(Josse-françois-
Joseph Le Riche)/L R
従ってそのビスクィの製作年代を、おおよそその刻印で類推出来ることになる。
<窯印と職人のマーク>
窯印と制作年ーヴァンセンヌ窯の1750年よりフランス王室ルイ(Louis)の L を重ねたモノグラムの窯印が、セーヴル窯でも1756年より、1793年まで使用された。
多くは青で釉上にで描かれており、1752年までは、ドットが入ったりするが、イアーマークは入らず、制作年は特定出来ない。
1753年よりアルファベット順にイアーマークが、やはり青の釉上に入る。但し、軟質磁器の釉薬は上絵の焼成時に、顔料が容易に釉薬内に溶け込み、一部イングレイズになる。
但し、1753年から1755年のブルー・ラピスのグランドカラーの作品では、釉下に窯印が描かれているものが存在する。これは本焼きの前の地色を塗っている段階で窯印を入れたものと思われる。
従ってセーヴル窯のイアーマークは、1756年のマーク D から始まり、1777年に Z 、1778年からはアルファベットを重ねて、 AA、BB、と1793年の PP まで続いていく。
そして1793年の7月16日より、フランス共和国(République Française)の RFが使用されるようになる(因みにフランス革命は1789年、ルイ16世は1792年に退位し、1793年の1月21日に処刑された)。
また1750年代から1760年代にこのモノグラムの上に、稀にクラウンが描かれることもあるが、1770年代以降は、このクラウンのマークは素地が硬質磁器である事を意味する。
硬質磁器自体は1768年より制作されているが、セーヴル磁器の軟質磁器作品は絵付けが素晴らしく、人気が高かったので、軟質磁器は硬質磁器と並行して制作し続けられた。
絵付け師と金彩師ー作品の品質、職人ごとの仕事量を管理者が管理する目的として、窯印と合わせて、絵付け師、金彩師のマークが釉上に入れられた。
作品によっては、非常に多くの職人が絵付けに携わっているが、 1750年代では、一人の絵付け師のマークのみの事が通例で、実際ほぼ一人の責任で絵付けをしたと考えられる。1760年代には、絵付け師のマークは、一つの作品に、二つのマーク(例えば、花絵担当と、風景画担当など)が入るようになり、更に1770年代に入って金彩師のマークも入れられる様になった。
そのため1770年以降では、時に金彩の窯印が入った物があるが、これは絵付け師が書き忘れて、金彩師が後から窯印を入れたものと思われる。
但し、絵付け師のマークの無い作品も非常に多く存在する。殆どのケースは不注意や、小品であったり、手のかかっていない作品のケースである。
しかし頻度は多くないものの、著しく手の込んだ作品や、格段に素晴らしい絵付けの作品に、絵付け師のマークが全く無いケースが存在する。
これは恐らく絵付け部門の主任クラスの手によるものと考えられる。絵付け師のマークをチェックする役割を担う者が、自分の作品に自分のマークを入れる必要性は全く無いと言う事である。
またこれら職人のマークは、必ず窯印の傍らに入れる事になっていて、その職人ごとに、窯印のどちら側かとか、どの辺りに入れるかの癖があった。
これら絵付け師、金彩師の職人の総数は、1800年までで385人が在籍したが、マークの分かっている職人は195人に過ぎない。この時期セーヴル窯には、68人の女性の絵付け師、金彩師が所属していたが、多くは男性絵付け師の娘や妻であって、彼女達はアシスタント的な立場で、ほんの6、7人以外は、自分のマークを持たなかったし、マークを入れる義務は無かった。