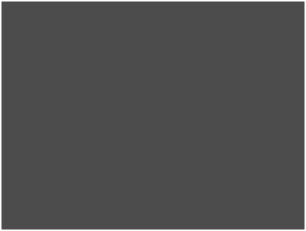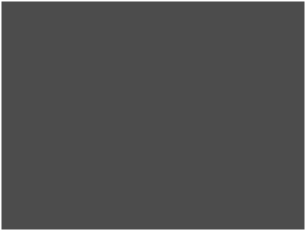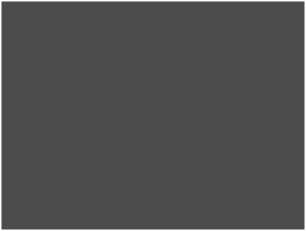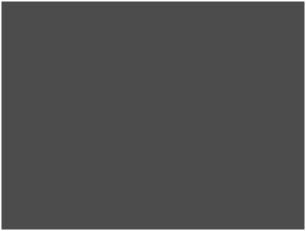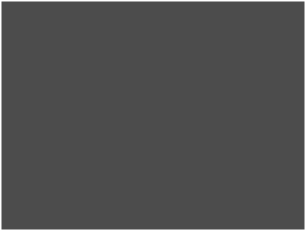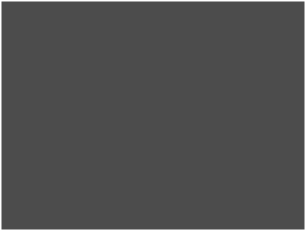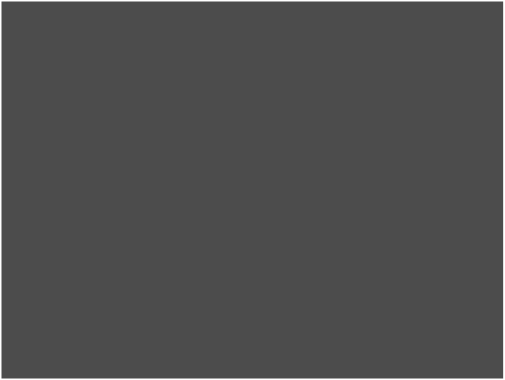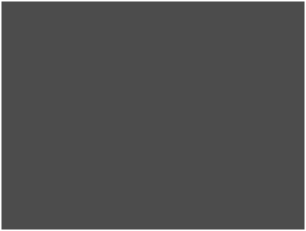日本、有田

日本における磁器の生産は、どのような時代背景で興って来たのか?
第14回西洋アンティーク陶磁器勉強会の資料を基に中国、ヨーロッパの関係から概説して行きます。
<中国の磁器輸出>
14世紀の元の時代に生まれた青花(染め付け)は、明の時代には景徳鎮の官窯を中心に発展した。15世紀には鄭和の大航海など、東南アジア、中東、アフリカまで、政府による交易を拡大した。景徳鎮には元時代から官窯(御器廠ぎょきしょう)が置かれ、これによって著しく技術が発展した一方、皇帝の為の官窯の増加は、かえって民窯の磁器生産を低下させていた。16世紀後半からの万暦帝の時代には、赤絵や、五彩等が発展したが、1619年に万暦帝が亡くなると、国内は混乱期に陥り、ついに1644年、景徳鎮からの磁器輸出は激減する。
一方16世紀に入り、西欧諸国は大航海時代を迎え、中国はポルトガル等と磁器の貿易が始まっていたが、16世紀末にはオランダがこの東方貿易に参入し、1602年には東インド会社を設立していた。
また中国から日本への磁器輸出は、16世紀前半に勘合貿易や琉球による中継貿易によって、また後半には中国船が活発に磁器の交易を行う様になっていた。但し1592年から98年の豊臣秀吉による朝鮮出兵でこれも一時途絶えていた。
このようにこの時期の中国の磁器輸出は、基本的に西のヨーロッパ(東南アジアから中東、アフリカ)と東の日本の二つの市場に向けて、両者の嗜好に合わせて行われていた。
<ヨーロッパの磁器輸入>
16世紀初頭にポルトガルは東方貿易を独占し、中国磁器を購入したが、磁器は必ずしも大きさや重さといい、効率のいい交易品でなく、中東地域への中継貿易が多く、ヨーロッパに流入した中国磁器の量は多くはなかった。しかし16世紀末にオランダが参入し、オランダは1602年には東インド会社を設立しイギリスも排除して、東方貿易を独占する。
オランダはカラック船で大量の中国磁器をヨーロッパに運んだが、これらのヨーロッパ諸国に対して輸出された中国磁器とは、主に染め付けで、いわゆる芙蓉手の意匠が多かった。器形は、ヨーロッパの食生活に合わせた皿や鉢(例えば食器をかけて置き易い鍔縁のスープ皿等は良い例と言える)が多かった。これらの中国磁器は、クラーク・ポルセレイン(Kraak Porselein)と呼ばれている。
また16世紀に始まったオランダの錫釉陶器デルフト焼きは、1612年頃には、すでに中国磁器の模倣を始めている。
<日本の磁器輸入の背景>
日本の磁器輸入は、12世紀の鎌倉時代、中国から帰国した禅僧栄西が広めた「茶の湯」の発展との関係が極めて深い。
室町時代、京を舞台に、上京では足利義政ら将軍家や公家の間で、日明貿易で輸入した高価な唐物を贅沢に使用した、華やかな茶の湯が流行した(東山文化)。一方、下京では庶民町衆の中で起こった、狭い茶室で、絵一枚、茶碗一つを「選びきる」、庶民の茶の湯、村田珠光らによる「侘び茶」が流行した。
村田珠光の侘び茶の精神とは、例えば満月の煌々たる光でなく、雲間に僅かに見える月の美を愛でるような精神であった。
この精神性は、戦国武将や、織田信長や豊臣秀吉を支えた大阪堺の町衆の間に受け継がれ、そして安土桃山時代に、この侘び茶を集大成したのが千利休であった。利休の侘び茶は、高麗茶碗を最高としていた為、朝鮮からの茶陶の輸入が盛んに行われるようになり、後の唐津焼(朝鮮陶工技術の移入)の開窯へと繋がって行く。そして更に唐津焼の諸窯より、後に磁器の生産が発展する事となる。
<日本の磁器輸入の変遷>
戦国時代が終わり、16世紀末から、武家社会では茶の湯が流行し、多くの陶磁器が輸入されたが、特に高麗茶碗への関心が高く、 1580年には、唐津焼が起こり、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際には、1597年、鍋島軍が朝鮮人陶工を連れ帰った。
明からは、15世紀には青磁、16世紀には景徳鎮で民窯の生産が活発化し、染め付け磁器が盛んに輸入されたが、日本の茶人の嗜好に合わせて、小皿特に左右非対称の変形皿や、碗や茶道具が、日本からの注文で作られた。これらが古染付である。また、景徳鎮民窯の赤絵や、もう少し安価な福建省南部の呉州手の染め付け(スワトウ)等が特に16世紀末から大量に輸入された。
1600年の関ヶ原の合戦以後も江戸時代に入り、利休、織部の侘び茶の嗜好はしばらく続くが、1632年に徳川秀忠の死後、三代将軍家光の茶の湯指南に小堀遠州が就くと、「綺麗さび」へと茶風が変遷した。輸入磁器も、従来の古染付から、祥瑞手へと緻密で繊細なデザインに、武家社会の嗜好も徐々に変化した。
<肥前での磁器生産の始まり>
豊臣秀吉の朝鮮出兵で鍋島軍が連行した朝鮮人陶工(おそらく陶器職人)は、近郊の泉山で磁土を発見し、1610年頃に磁器焼成に成功したと言われている。しかし最近の知見では、有田町西部に分布する唐津焼陶窯で、唐津焼と平行して1610年頃から磁器の生産が始まったと推測されている。この時代の磁器を初期伊万里磁器と呼んでいる(−1640年)。土質の問題、朝鮮系の特徴により、多くは厚手で三分の一高台で、面取りモノが多く、初期には、胎土目積み、砂目積み(当時朝鮮での陶器の技法)で窯詰めされたため、その目後が残る。当時朝鮮では染め付け磁器はまだ無く、初期伊万里は景徳鎮の古染付をモデルに製作されたと思われる。したがってその意匠は古染付にならい、水墨画によく描かれる、山水、花鳥、人物(中国故事、道教、仏教関連など)が染め付けで描かれた。
しかし初期伊万里の当初の生産量は、1630年代までは、明からの輸入磁器の国内需要の不足を補う程度であった。
1637年、山本神右衛門による、鍋島藩諸窯の整理統合が行われ、有田地域全体での分業化が進み、後に「内山」と呼ばれる窯業圏となって、本格的な生産体制が整えられた。同じ窯での唐津焼と磁器の同時生産もここで終焉する。これは国内の磁器需要に、藩内の磁器生産(大きな税収が得られる)が応えられる様、鍋島藩が整備統合したものと思われる。
<鍋島藩の献上磁器>
鍋島藩の当主鍋島勝茂は、1600年の関ヶ原の合戦では西軍側についた外様大名であった。当時の外様大名は常に改易のリスクに怯え、その為将軍家への献上品の確保や、外様大名の江戸屋敷への将軍の訪問「御成」への備えの為、磁器は欠かせない物となっていた。鍋島藩に限らず、北九州諸大名はその地理的利点から、茶道具等の中国磁器の輸入を盛んに行い、将軍家へ献上したり、北前船で各地に輸送して利益を上げていた。この時代、将軍の御成の時の宴席のため、山辺田窯等では40cmを超える大皿が生産されていた。(山辺田窯は、1650年代に御道具山の鍋島窯に陶工を引き抜かれたか、その後衰退する。)
1637年、島原で天草四郎の乱が起こると、鍋島藩はここで大失態を演じ、懲罰を受ける。(逆にオランダは幕府に加勢し、同じクリスチャンでも宗派の違うカソリック教徒を砲撃し、幕府の信頼を得た)この後1639年からは日本は鎖国に入り、オランダと中国以外とは貿易出来なくなった。そして1644年、清が起こって動乱の為に中国磁器輸入が激減すると、鍋島藩は献上磁器の供給が不足し由々しき事態に陥った。
<鍋島藩の磁器輸出と献上伊万里>
1644年、中国からの磁器輸入が止まり、存亡の危機に陥った鍋島藩は、自前で中国磁器に匹敵する磁器を制作する道を選んだ。1650年頃より、御道具山に官窯を築き、将軍献上手の鍋島焼の生産が開始された。
一方、中国からの磁器が入らなくなったオランダや、これまで利益を得ていた中国人商人は、日本の磁器の生産状況に目をつけ、鍋島藩内の民窯との貿易許可をとった。
当時の有田諸窯では、染め付けのほか、白磁、瑠璃釉や、鉄釉、辰砂、1630年から青磁、1640年頃から、中国人陶工から習得した色絵磁器も生産出来る様になっていた。
また轆轤ー型打ち、糸切り成型付け高台、型押し、板作り成型や、灰降りを防ぐ、サヤ作りなど、焼成技術も進歩していた。
1647年、初代酒井田柿右衛門が、長崎の中国人(戦乱で流出したか?)より赤絵技術を伝授され、いわゆる赤絵磁器の制作に成功した。
柿右衛門窯は元は内山地区年木山(としきやま)(泉山)の楠木谷窯(乳白手の白磁が出土している)に在ったが、1750年頃に外山地区の下南河原山(しもなんがわらやま)に移った陶工集団と推測される。
<有田からヨーロッパへの磁器輸出>
オランダの東インド会社(VOC)は、有田の民窯諸窯と貿易し、中国磁器の供給不足を補おうとした。
1650年頃から、オランダは有田磁器を買って東南アジアでこれを売っているが、1659年に最初の大量の買い付けを行った。これはオランダまで運ばれたが、不評であったらしい。その為見本として、中国か、デルフト陶器の中国磁器写しを有田側に提示し、それと同じモノを作らせた。
これはおそらく明時代にカラック船で持ち込まれた、ヨーロッパの器形で芙蓉手の意匠のものであったと思われる。
逆に有田側が初めに送ったものは、古染付や、天啓赤絵の写しものではなかったかと思われる。 1660年、オランダに運ばれた11530個の中に、新しい器形として、四角鉢、八角皿等が登場している。
一方、ここで指摘しておかなければいけない事は、中国人商人は、この時期にオランダの2倍以上もの有田磁器を、ヨーロッパに中継貿易していたという事である。
<柿右衛門(延宝)様式の成立>
1647年頃から清朝に抵抗を続ける鄭氏らの中国船が、有田磁器を東南アジアへ中継貿易していた一方、1659年にはオランダの大量注文があり、その後、中国磁器よりもより白い素地、例えば徳化窯のような磁器の注文があり、その結果南河原の酒井田家によって「乳白手」「濁し手」(ニゴシデ)の柿右衛門の素地が開発された。
この素地は、素焼をし、可能な限り釉薬から青み(鉄分)を取り除き、薄くそれを釉薬として掛けた素地で、染め付けでは呉須が黒く発色してしまう。その為、典型例では青は上絵付けで塗られている。
1670年頃に乳白手の柿右衛門様式は完成し、絵付けの輪郭線は、その為に鍋島焼の染め付けに対して、柿右衛門では黒色で描いている。彩色は、赤、緑、青、黄、金、紫で、鍋島窯が抽象的、幾何学的文様が多いのに比べ、柿右衛門では現実的な意匠表現をしている。1670−1690年頃の典型的な柿右衛門様式では、素地は乳白手で、轆轤ー型打ち成型で、口錆が施され、意匠はアシンメトリックな構図、「間」という空間が設けられており、古田織部の不定形な造形にも通じる作風と言える。
<柿右衛門様式の終焉>
しかし1670年に成立した柿右衛門様式の輸出製品は、1690年代から急速に姿を消して行く。
①1684年から清朝康煕帝による遷海令の解禁で、景徳鎮の海外輸出が再開し、高騰してしまった柿右衛門磁器に比べて極めて安価な、Famille verte などの緑色系粉彩の色絵が大量に出回った事。
②将軍家綱に替わり御成が増え、鍋島焼の水準を上げる為に柿右衛門窯から陶工が引き抜かれた可能性がある事。
③国内での趣味の変化、富裕商人が増え、金蘭手などを好む様になった事等が理由として考えられる。
1690年代以降は、アシンメトリックな構図が崩れたり、空間が絵文様で埋められたりする傾向が見られるようになる。
1710年より、中国伊万里が作られる様になり、中国商人は有田磁器を扱わなくなり、 1740年には有田磁器は市場を失っていく。
実は当時のヨーロッパ人には、有田磁器と中国磁器の区別が、ほとんどなされていなかった。
<日本の磁器輸出の衰退>
日本の磁器輸出は18世紀に入って、古伊万里様式などの染付けの上に金彩をするという新しい装飾様式を生み出すが、これらもやがて中国磁器に模倣される。
オランダ東インド会社も、一度は排除したイギリスが再び東南アジアで勢力を持ち、更に本国は三度に渡る英蘭戦争で、経済的に大打撃を受け、日本からの磁器の輸入量も減らして行った。
1709年ヨーロッパでもザクセン公国のマイセンで磁器の焼成に成功すると、瞬く間にヨーロッパ中で磁器が生産されるようになり、ますます輸出量を減らし、有田の諸窯は、国内向け市場をターゲットにした生産に切り替わって行った。